公開日: 2025/04/24
更新日: 2025/05/09
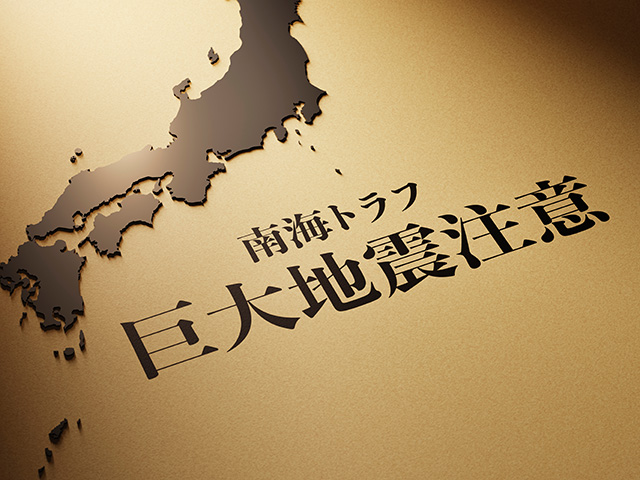

何気ない平和な日常が突然変わってしまう。これが大災害の恐ろしさである。阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、地震による影響は今なお各地に大きな爪痕を残している。そんな日本で今対策しなければならないのが、南海トラフ巨大地震だ。
政府の地震調査委員会によると、南海トラフ巨大地震は約100~200年の間隔で起きており、直近では1946年に発生。現在はそれからすでに約80年が経過している。同委員会は1月15日、今後30年以内に発生する確率を、これまでの「70~80%」から「80%程度」に引き上げた。またこの巨大地震について、南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会は3月31日、新たな被害想定を公表した。
南海トラフ巨大地震は、静岡県の駿河湾から九州の日向灘にかけてのプレート境界「南海トラフ」沿いで発生すると想定されている地震。最大震度は東日本大震災と同等のマグニチュード9クラスの揺れが起こると予測している。
3月に公表された被害想定では最悪の場合、死者数が29万8000人、避難者数は1230万人にのぼるという。また今回、災害による負傷の悪化や、避難生活による身体的負担が原因で亡くなることを意味する「災害関連死」の試算も公開。これによると、該当者は最大値で東日本大震災の10倍を上回る5万2000人に及ぶという。

いつ起こるか分からない巨大地震で生き残るためには、一人ひとりの防災対策が求められる。特に南海トラフ巨大地震では津波による大きな被害が予想されているため、避難所への経路確認が重要だ。防潮堤があるから大丈夫と油断せず、迅速に避難する必要がある。ただこの時、津波警報の発表以降に避難することはお勧めできない。通常、津波警報は地震が発生してから約3分を目標に発表されるが、南海トラフ巨大地震の場合、津波の最短到着時間が2分と予測されている地域もある。地震発生後にすぐ避難するためにも、事前に避難所を調べるなど準備を進めておくべきだろう。
南海トラフ巨大地震による影響は津波被害だけではない。富士山を含めた火山の活発化や噴火の可能性があるのだ。1707年に発生した宝永地震の時は49日後に富士山が噴火。当時の江戸まで火山灰が降るほどの大規模な災害となった。東日本大震災後も東北や東日本にある複数の火山が活発化した例から、富士山が噴火する可能性は捨てきれない。地震発生後も油断は禁物だ。
今回紹介した防災対策はあくまで一例であり、このほかにも様々な準備や対策をすることができる。家族と共に避難所を確認し、連絡方法について共有することも良い対策となる。例えば災害用伝言ダイヤルは、「171」に電話をかけることで安否などの伝言を残すことが可能だ。能登半島地震では震災直後、停電や通信設備の被害により連絡が取れず、多くの人々が家族の無事を確認できない状況に陥った。まだ準備しなくても大丈夫とは思わずしっかりと話し合い、防災意識を高めることが大切な人の命を守ることに繋がっていく。



人気記事ランキング