公開日: 2025/09/23
更新日: 2025/09/26
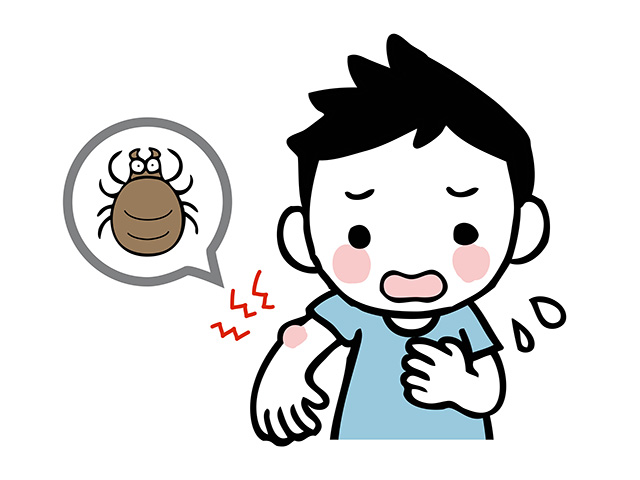

木々の葉が色づき、紅葉で山々が華やかになる秋は絶好の観光シーズン。この時期になると山や森など、自然を眺めることができるスポットが人気だ。だからこそ、気を付けなければならないのが、マダニによる感染症である。国立健康危機管理研究機構(JIHS) は8月10日、マダニを媒介して感染する「重症熱性血小板減少症候群」(SFTS)の発症者が135 人を突破したことを発表した。これは、過去最多であった2023年の134人を上回る人数だ。
SFTSは、2011年に中国で発見されて以降、2013年から日本でも患者数が増加している感染症だ。主な初期症状は、発熱や倦怠感、消化器症状。重症化すると、出血が止まらなくなるほか、意識障害や腎臓と肝臓の障害が発生し、最悪の場合、死亡する可能性がある。JIHSが公開している、2013年3月~2024年4月までの感染症発生動向調査を見ると、国内での感染報告数は963件なのに対し、死亡例は106件。報告後に死亡した例なども合わせると、致死率は27%になるという。これまで、主に西日本で発症者が確認されてきたが、今年に入り北海道や関東でも報告されている。

SFTS以外にも、日本で確認されているマダニを介した感染症は様々。頭痛や発熱などを伴う「日本紅斑熱」や、インフルエンザのような症状を引き起こす「ライム病」などの病気が存在しており、全国で感染者が確認されている。また、髄膜炎や脳炎などを引き起こす恐れのある「ダニ媒介性脳炎」は、ファイザーの発表によると、北海道において2024年8月までの間に7例の人間への感染が報告されている。この事実からも、今後は国内のどの地域でも感染するリスクはあるものと考えられる。
このように感染症を媒介するマダニだが、生息場所は山や森といった自然から、公園や庭といった身近な場所まで、屋外の様々な草木に潜んでいる。3月~11月までの期間、エサである人間や動物の血液を求め、活発に活動。体長は2~3mm程度の大きさだが、自身の体重の100倍以上もの血液を吸うことが可能だ。長時間吸血するため、中には10日以上噛みついていた事例もある。また、唾液には麻酔に近い効果があり、痛みを伴わないことから噛まれていても気付きにくく、発見が遅れることが多いという。
冒頭の話に戻るが、自然を感じられる観光スポットだけでなく、趣味としてアウトドアを楽しむ人もマダニに注意する必要がある。無論、ツーリングを楽しむライダーも例外ではない。長袖長ズボンを着用して肌の露出を防いだとしても、マダニが服に付着していた場合、着替え中に噛まれる可能性があるのだ。
また、犬や猫といったペットにも気を付けなければならない。不用意に素手で触れてしまえば、ペットに付着していたマダニに噛まれてしまう恐れがある。そのため、散歩などで不用意に草木に近づかないよう、注意する必要があるだろう。
もし草木の多い環境に行くことがあれば、帰宅時にガムテープなどで服を掃除するほか、入浴時にマダニに噛まれていないか自身の体を確認することが重要だ。感染予防のためにも、マダニ対策の徹底が求められる。



人気記事ランキング