公開日: 2025/10/07
更新日: 2025/10/09
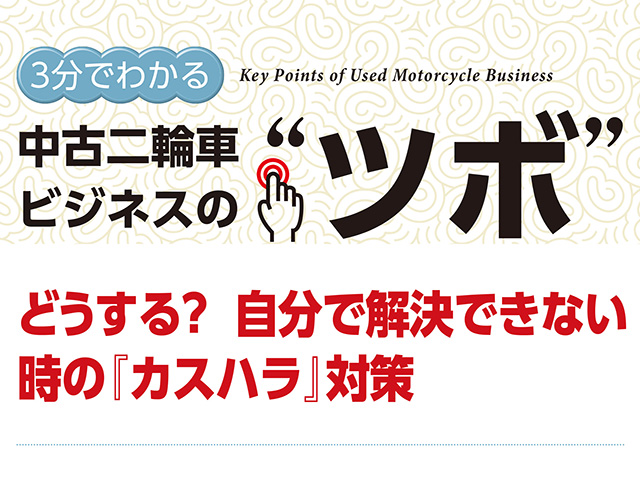

昨今、何かと話題になるのが『カスタマーハラスメント』、略して『カスハラ』。今年6月、事業主にカスタマーハラスメント対策を義務付けることが盛り込まれた『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律』が可決された。それだけカスハラは、モラルやマナーでどうにかなる範疇を越えており、法整備が求められるほど深刻化しているのである。

報道では、スーパーや飲食店の例を取り上げられることが多いが、接客が必要となる業種・業務なら、どの現場でもカスハラは起きうる。それは、二輪の新車販売店でも中古車販売店でも変わらない。以下の話は、東京都のある中古車販売店Aで発生した事例だ。
マフラーの交換を希望するユーザーが来店。乗ってきたバイクは販売店Aで購入した車両ではなかった。買った店が遠いので、ユーザーの自宅から近いA店に来たのだという。マフラー自体は持ってきておらず、他店で購入したものを後日、発送するとのこと。届いたら、その商品に換装し、外したマフラーは、そのユーザーが指定した場所に送るよう依頼された。その返送先はユーザー宅ではなく、ユーザーの友人宅だった。
だが、マフラー交換後、元のマフラーをスタッフが間違ってユーザー宅に送ってしまったという。すると、ユーザーが激怒し、「どういうことだ!」と電話してきた。
返送先を間違ったのは店側なので謝罪するとともに「受け取りに行きます」と伝えたが、そのユーザーは「バイクショップが変なモノを送りつけてきた」と警察に通報。通報を受けた警察が店に来たので事情を説明したところ「双方で話し合ってください」とのこと。改めて受け取りに伺うことを伝えたらユーザーの了解が得られたので受け取りに行った。すると、今度は「敷地内に不審者が入り込んでいる」と、またもや警察に通報されてしまった。

ユーザー宅の敷地内に勝手に入り込んだのではなく、マフラーを受け取りに来ただけであることを警察に説明して事なきを得たが、そのままでは受け取りに行くこともできないので、店に着払いでマフラーの返送をお願いしたというが、それも断られるといった状況。もう、店としてはどうにもできないので「どうしたらいいのか」とユーザーに尋ねたところ「誠意を見せろ」と言ってきた。そこで「誠意とは何か」を聞いたら『金銭』だという。それを断ったところ、店に誠意を催促する電話が頻繁にかかってくるようになった。
それがしばらく続いたので、もう、自分で解決するのは無理だと思い、ユーザーに「このままでは埒が明かないので、これ以上、金銭を要求する電話をかけてくるようなら、カスタマーハラスメントとして、知り合いの弁護士に相談します」と伝えたところ、毎日のようにかかってきた電話はピタッと止まり、それ以降は一切連絡がなくなったという。
たとえ理不尽な要求でも、相手(この場合は店側)に非があると感じたら、どんな要求も許される、どんな要求も受け入れなければならない、と思ってしまう人は一定数いる。そして、話が長引けば長引くほど、相手の要求がエスカレートしていく。店がいくら誠実に対応していても、理不尽な要求が目的であれば、話は複雑化する。
この一件は極端な例かもしれないが、似たようなことを経験している二輪販売店は、決して少なくないだろう。今回のような場合、店だけで解決することはほぼ不可能だと言っていい。だからといって、耐え続けなければならないということもない。店が最もやってはいけないことは、ユーザーとともにヒートアップすること。当事者同士だけで話し合うのではなく、ワンクッション置くことで冷静になることもある。話の収拾がつかなくなった時は自分でどうにかしようとせず、「弁護士に相談します」など、第三者に頼ることも必要、ということを頭に入れておくといいだろう。


人気記事ランキング